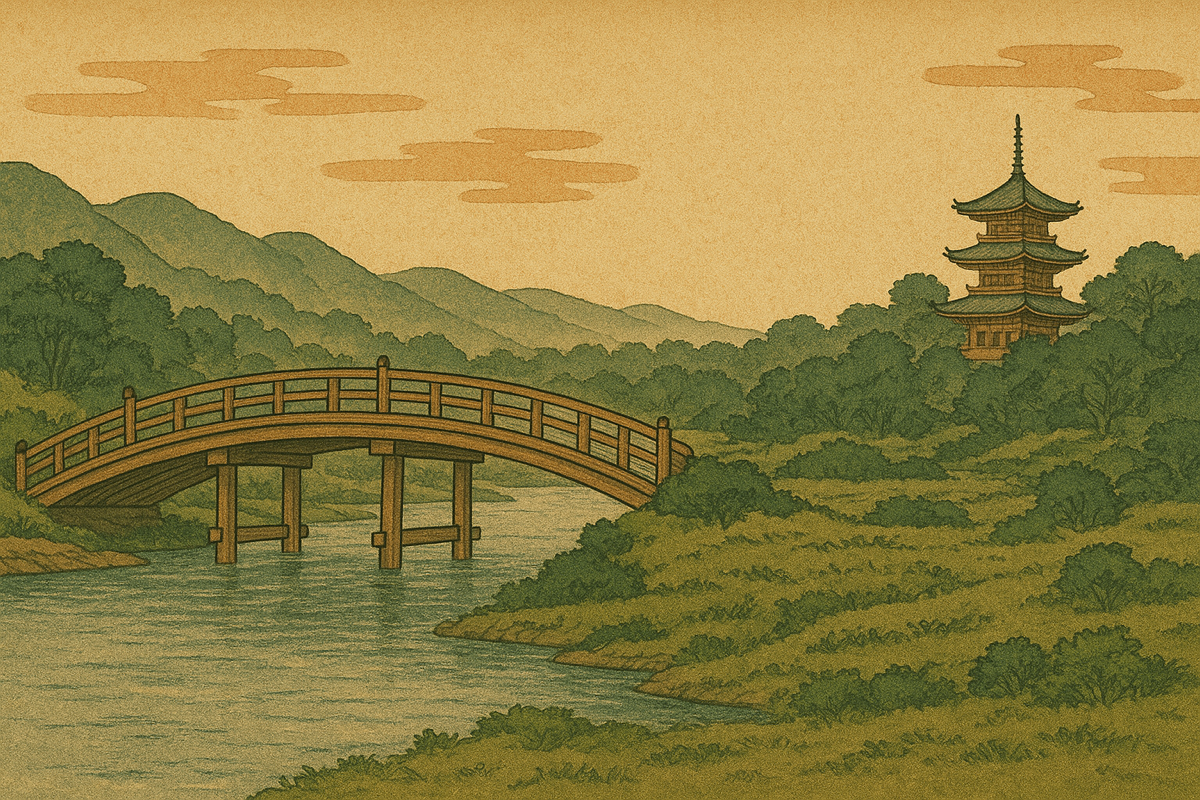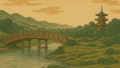2025年大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』が、いよいよクライマックスを迎えようとしています。
主人公・蔦屋重三郎は、江戸の町人文化を盛り上げた言わば“出版界の革命児”で、アイディアを絞り出し、夢に向かって大胆に立ち回るのを、胸のすくような思いで楽しんだ方も多かったのではないでしょうか。
蔦重はこれまでのお話で、私達もよく知る浮世絵師や作家をたくさん世に送り出しており「この人も、この人も蔦重に見いだされた人だったのか。」と、私は国語や美術、歴史の教科書を振り返ったりしました。
さて、そんな大活躍の蔦重が最終章ではどうやら「夢の代償」とも言える試練に立ち向かっていくようですが、果たして蔦重はそれを乗り越えられるのでしょうか。
この記事では、史実の蔦屋重三郎の最期や伏線も読み解きながら、『べらぼう』の結末を徹底予想してみます。
史実での蔦屋重三郎の最期とは?
史実によると、蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)は 1797年(寛政9年)頃に没 したとされています。
この時蔦重は47歳、思ったより若くして亡くなっています。
正確な死因は記録に残っていませんが、「ふんどし」こと松平定信による厳しい罰則を受けた上に「身上半減」されたるシーンが思い出されますが、その江戸後期の出版統制「寛政の改革」によって事業が打撃を受け、経済的に困窮したとも、当時江戸病と言われた脚気によって命を落とした、とも言われています。
彼は黄表紙や洒落本、浮世絵など“庶民の笑いと美”を扱った版元であり、その自由な表現が幕府の検閲に触れたことをドラマの中で印象的に描かれていました。
時代を駆け抜けるように太く短く、生きたということでしょうか。
史実の蔦重は「文化のために命を削った商人」という点が、最終回のテーマが見え隠れします。
ドラマに散りばめられた伏線まとめ
『べらぼう』の中では、いくつかの気になる伏線が描かれています。
- 第23話:「我こそは江戸一利者なり」では、蔦重の“商人としての信念”を強調
- 第25話:「灰の雨降る日本橋」では、浅間山の噴火が象徴的に描かれる(崩壊の予兆)
- 第26話:「三人の女」では、蔦重を支える女性たちの想いが交錯
これらの要素はすべて、「夢の代償」「文化の継承」という最終回のテーマにリンクしている気がしてきます。
SNSでのファン予想まとめ
X(旧Twitter)や掲示板でも、「蔦重の最期」に関する考察が白熱しています。
「べらぼう、最後は悲しいけど美しく終わりそう」
「史実通りに亡くなるより、文化が受け継がれていく描写で締めそう」
「歌麿や京伝たちが“蔦重の夢”を継ぐ形になるのでは?」
多くのファンが、“死で終わる”よりも“志の継承”を表現する結末を予想している…というより、あの突き抜けた明るさを持つ蔦重らしく、暗い最期ではないといいなと期待しているように思えます。
筆者予想!大河『べらぼう』の結末はこうなる
筆者の予想では、最終回は「蔦屋重三郎の死」そのものではなく、彼の理念を受け継いだ人々の姿で締めくくられるのではないかと思います。
例えば──
- 歌麿や京伝、吉原の「忘八」達が、蔦重の残した絵や言葉を手に、江戸の町で笑顔を取り戻す
- なんなら江戸の町中で踊るお祭り騒ぎで幕を閉じる
- 未来の出版文化や現代の私たちに繋がるということを、九郎狐綾瀬はるかさんの爽やかな“ラストナレーション”で締めくくる。
江戸中を楽しませ江戸中に愛された蔦重の夢が、未来へ繋がっていくようなラストを期待せずにはいられません。
まとめ|“夢”を遺した男・蔦屋重三郎
『べらぼう』の魅力は、江戸の人たちが“身分の壁”を越えて文化を広めたこと。そしてその身分の壁を乗り越える時の人々の姿は真に生き生きと描かれました。
源内先生しかり、田沼意次しかり。そしてそれをドラマで見る「未来」の私たちは、私たちの未来をも夢や希望を持って見つめることができたのではないでしょうか。
蔦屋重三郎の生涯を描いた物語は、単なる歴史ドラマではなく、「創ること・伝えることの意味」を現代に問いかける今まさに私たちが直面しているテーマでもあります。
最終回放送後には、改めて「蔦重が残したもの」を振り返る記事も更新予定です。📺 続報が入り次第、この記事にも追記します!