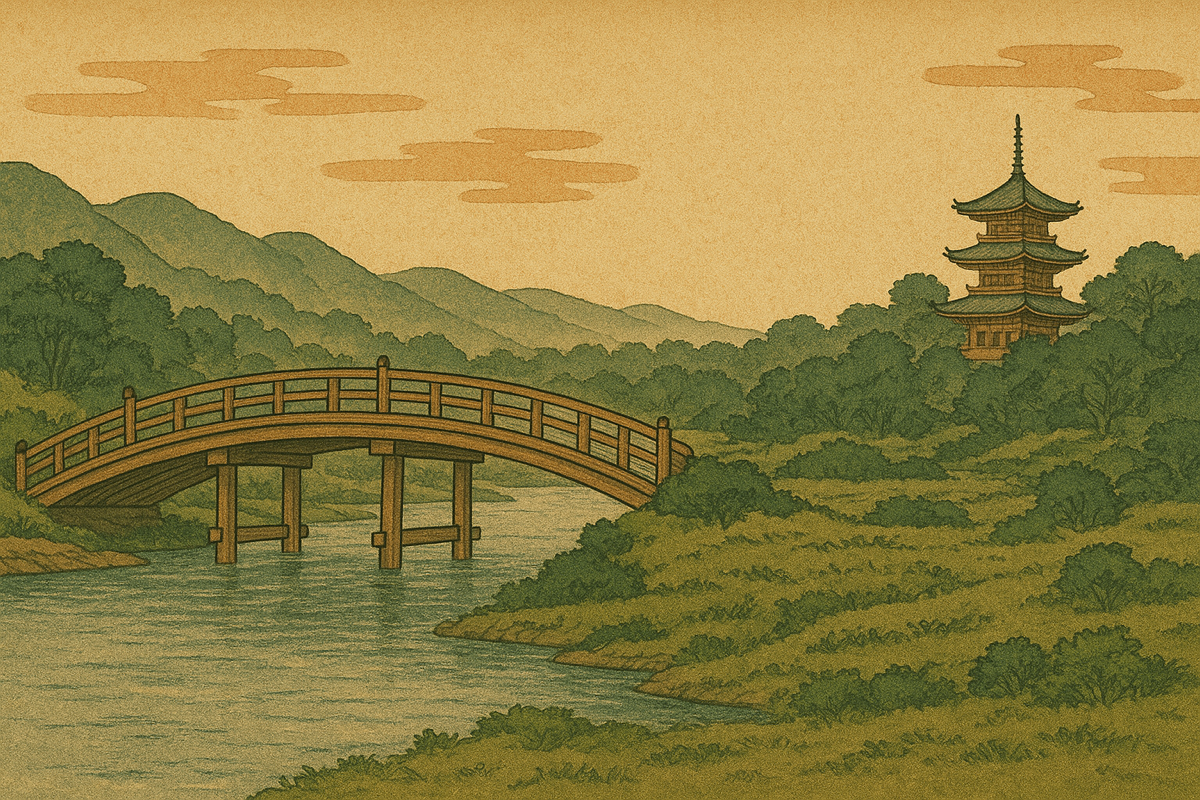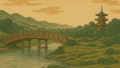1.ドラマ「べらぼう」おさらい
「べらぼう」は蔦屋重三郎(通称:蔦重)を主人公に、江戸後期の出版業界・絵師・商業文化をとりまく人々を描いた作品です。タイトル「べらぼう」は江戸語で「途方もない/すごい」という意味合いがあり、蔦重の“べらぼう”な夢や生き方を表しています。
2.歌麿&写楽ってどんな人?
喜多川歌麿
美人画を得意とした浮世絵師。蔦屋重三郎と関わりが深く、ドラマの中では蔦重を慕い、兄弟のように過ごした時期もあるという設定。町人文化や女性像を繊細に描いて人気を博しました。
東洲斎写楽
役者絵で知られる謎の絵師。1780年代後半に突如現れ、短期間で多数の傑作を残して忽然と姿を消したことから、長年にわたり「写楽の正体は誰か?」という議論が続いています。
3.“歌麿=写楽”説が出る理由
- 蔦屋重三郎という共通の版元:歌麿・写楽双方に関係のある版元が共通している点が、同一人物説を生み出す背景となっています。
- 写楽の正体が不透明:わずか1年ほどの短期間の活動とその後の消息を絶っており、別名か変名で活動した可能性が高いとも議論されています。そのため江戸最大の謎の絵師と呼ばれています。
- 活動時期が近い:寛政期を中心に活動した時期が重なり、同一人物説ではないかという想像を掻き立てられます。
- 版元による“演出”の可能性:版元は江戸のメディアプロデューサーでもあり、名前を変えて異なる作風を提示することは不可能ではありません。
- 写楽役がキャスティングされていない:明らかに写楽が登場するはずの舞台があるのに、写楽役の俳優さんが発表されていないのは、歌麿が写楽だという設定だからでは?
4.ドラマ視点での読み解き
ドラマ「べらぼう」は蔦屋重三郎を“江戸のメディア王”として描いています。物語上、ひとりの絵師が異なる顔を持つ(=別名で活動する)という筋立ても自然に組み込めます。そこに視聴者は「このシーンは写楽を匂わせている?」と期待が膨らむのです。
例えば、美人画で有名な歌麿ですが、ドラマでは「美人画ではないリアルな女の人を描いた絵」がありました。それが写楽の大首絵の画風を思わせるような絵だったと思いませんか?
5.反論・注意点
学術的には写楽=歌麿という単純な結論を出すには至っていません。作風の差異、資料の不足、写楽が集合名義だった可能性など、複数の説が存在します。ドラマはあくまでもフィクションであることを踏まえ、史実と違うのをあえて楽しむことや、史実と混同しないことも大切です。
6.まとめ
みなさんはどう思いましたか?
私は結論よりも「楽しみ方」としてこの説をとらえてみました。ドラマを見ながら「写楽の痕跡はどこにある?」と探したり考えたりすることで、江戸の出版文化や浮世絵の面白さをより楽しみつつ視聴したいと思います。